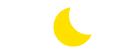本書は、小説「春の城」本編と、その取材過程を記した紀行文「草の道」、そのほか執筆にまつわるエピソードや識者の解説などからなる。まるで辞書のように分厚い総900ページの大著だ。小説自体は島原の乱の話である。石牟礼道子は、水俣の患者たちと東京のチッソ本社前の道端に座り込みをしたときから、この作品を書こうと思ったという。患者たちの長年の受難とそれに対応してきた人々(チッソ、国、国民)を見てきて、「冬の寒い時に明日のあては何もないのに、食べ物もお金も何もないのに、チッソの前に座って、患者さんたちといっしょに、飢え死にしたって、あるいは機動隊にぶっ叩かれて、引きちぎられて死んだって、なんていうことはないなと思っていました」とのこと。その思いが、400年の昔、幕府に対して一揆を起こした天草・島原の民百姓につながる。年寄り、女子供を含めた三万七千もの一揆勢が原(はる)の古城に立てこもり、幕府軍十二万を迎え討って全滅した。1638年の春のことだった。それは年貢の軽減を求める一揆ではなかった。はなから死を覚悟した戦いだった。いったいどういういきさつで、ただの百姓たちが、はるばるやってきた幕府軍を迎え、最後まで屈しなかったのか。石牟礼は、その精神性というか、人間の中にある聖性をさかのぼって、どこまでとらえられるか表現しておきたかった、と述べている。
作品にはたくさんの人物が登場する。村々の庄屋、百姓、作人、弁指しと呼ばれた漁師の元締め、半農半漁の零細民、浪人の身の切支丹武士、長崎の商人、仏教徒の女、僧侶、子守の子どもなどなど。石牟礼はその一人ひとりの生を描きつつ、本当に食べる生きるの生活を詳細に描きつつ、彼らが一揆に収束していった内面をていねいにたどっていく。読み終わって、詰まるところ、立ち上がった人々は自分自身を生きるために死を選んだのではないか。そうすることでしか自らを救えなかったのだと思った。水俣病、沖縄基地問題、福島原発事故・・、大きな力の前に、実は国民全体の問題なのに、一部の人々が集中的に災いを被る、「受難」は今の時代にも確かにある。
それにしても、改めて文学の力のすごさを感じた。歴史学は事実・真実を追究して歴史的意義の解釈を加えるが、その事象に関わった人々の精神性まで論じることはできない。それに迫るのは文学の仕事である。「苦界浄土」しかり。「西南役伝説」しかり。石牟礼道子はそんな仕事をした。そして昨年90歳で亡くなられた。