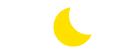大著である。「各時代の日本人は、抽象的な思弁哲学のなかでよりも主として具体的な文学作品のなかで、その思想を表現してきた」とする著者は、各時代の文学作品を読み解く作業を通して、日本文化とは何かという壮大なテーマに取り組む。
上巻は古事記・日本書紀から元禄文化まで。著者の論述はいわゆる文学作品の枠を越え、鎌倉仏教思想や江戸期の朱子学などにも及ぶ。すなわち文学作品を基軸として見た日本思想史というべきか。驚くべきは取り上げた作品の数。少なくともこの上巻では歴史上残っているほとんどすべての作品と思われる。それぞれの時代や特定の作品に関する専門家はあまたいるだろうが、我が国に伝わるほとんどの文字資料(美術・造形作品も)に目を通し、全体としての日本文学史論を単独で展開した人は加藤周一氏の他にそうはいまい。「序説」という書名は概論という意味合いだろうが、それを一人でやってのけるところがすごい。作品全体を通して日本文化の土着性、仏教をはじめとする外来思想がこの国で変化しながら受け容れられていったことなどが述べられている。著者の関心の出発点でもあるが、日本人とは何かを考えさせてくれる本。