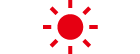作品の「時代」はなんと紀元前3万年ごろ(洪積世最終氷期)。場所はヨーロッパのクリミア半島あたり。ネアンデルタール人の部族に拾われ育てられることになったクロマニヨン人の少女エイラの成長の物語である。作者は想像力を存分にはたらかせ、原始の世界を実に詳細に描いている。そのことに圧倒される。
エイラの成長とともに物語はおもしろさを増し、ぐんぐん引き込まれていく。特に、エイラが女には禁じられていることを知りながら石投げ器を用いた狩りをおぼえ、ある偶発的な出来事からそれが一族の知るところとなって彼女の裁きをどうするかという場面などは、非常に緊迫感がある。エイラが死の呪いを受けたときのイザ(エイラの育ての母)やクレブ(エイラを庇護するまじない師)の悲しみに満ちた振る舞い、そしてエイラの生還は感動的だ。
エイラには次から次へと試練がふりかかる。が、エイラは旧人類(ネアンデルタール人)の伝統や存在そのものをゆさぶりながらたくましく生き抜いていく。7年に一度開かれる氏族会、そこでの氏族のリーダーを決める競技、そして育ての母イザの死。物語は克明に語られ、読み手はまったくエイラに同化するので、イザの死には本当に深い悲しみを味わう。リーダーの地位に就いたブラウドは、絶対的な権力をかざしてエイラからデュルク(エイラの子)を引き離し、呪いをかけてエイラを氏族から追放しようとする。そしてまさにその呪いがかけられようとするとき、大地が大きく振動し、クレブが死ぬ。氏族を追われ、たった一人で旅立つエイラに「マーマ、マーマ」と呼びかけるデュルクの声・・・。『始原への旅立ち 第一部 大地の子エイラ』はここまでだが、物語はまだまだ続いていく。この長い物語の圧倒的な迫力は大したものである。